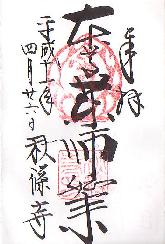秋 篠 寺
大和の風情・気品あふれるしっとりの寺
ここからまたまた旅気分
破石町バス停からバスで近鉄奈良駅へ戻り、ひと駅先の大和西大寺駅へ。ここからバスで秋篠寺へ向かう。
秋篠寺は静かで上品なところだ。オトナっぽい。新薬師寺はコドモっぽい寺だった。坊さんはなんだか落ち着きがないしやたらと貼り紙があるしメリーゴーランドだし外人ファミリーが来るしフラッシュぴかぴかシャッターばしゃばしゃだし(それはそれで面白かったんだけど)。だから余計に秋篠寺をしっとり落ち着いた寺だと感じるのだろう。東門から入り木立の中を通って本堂へ向かう間も、すれ違う人と目礼をして行き交う。木々の葉が風に揺れる音を聴く。はぁ〜、オトナっぽい。 伎芸天に逢いに来た 本堂に入るとすぐに目に入る伎芸天を見て、胸が押し潰されるような衝撃を受けた。なんと言ったらいいのだろう、伎芸天!このたたずまいの美しさ、写真で見るより、実物は100万倍イイ!何がどうイイのか、どう表現すべきか悩みに悩んだ末にやっぱりホントにお手上げなので、代わりに、受付でもらった「秋篠寺小誌」というパンフに載っている歌を紹介しよう。 
諸々のみ佛の中の伎芸天
指、ひざの曲げ具合、左下から見上げる左目の下あたり、やさしい微笑み、かしげた首、ちょこっと見えるヘソまわり。 まったくもって、匂ひこぼれて立たせ給へりだ!
いやなヤツらを見てしまった
外でワイワイと団体の襲来の気配がする。はしゃいだ声なので修学旅行生だとばかり思っていたが、入ってきたのはおじさんおばさんの団体だった。いや、おじさんというよりおじいさん。おじいさんたちは修学旅行生以上にべちゃくちゃとうるさい。みんながそれぞれに間違った識別と勝手な解釈で仏像に対する感想をいちいち口にする。伎芸天を見たおじいさんは、「なんだ芸者か。品がない」と吐き捨てるように言った。・・・と、どこからともなく案内人が登場した。50代くらいの男で、手には白手袋をはめている。白手袋男はうるさい団体に向かって仏像の見方の基本を説き始めた。如来菩薩天部明王などの区別や三尊像の組み合わせについて簡単にまとめて説明したあと、伎芸天の前に立ち、 「伎芸天の像は非常に珍しいんです。この美しさは数ある仏さんの中でも最高のものです」と静かに言い切った。するとさっき品がないと言ったおじいさんも含め、全員が一斉にハァーっとためいきをついて「そう言われりゃそうねぇ」「うん、なるほどきれいだ」など口々に感嘆している。キライだ、こいつら。 やつらが立ち去り静寂が戻った 壁際まで下がって伎芸天の全体を眺めたり近寄って細部をじっくり見たりを何度も繰り返していたら、壁際に腰掛けて双眼鏡で伎芸天を凝視していたおじさんが話しかけてきた。伎芸天を好きなのか、とかそういった前置きも何もなしに、「私なんか毎日この人に会いに来てますよ」といきなり言うのだ。この人とはもちろん伎芸天のことである。キミも伎芸天を好きだということは訊かなくったってわかるわい、という理解がこのいきなりの語りかけには含まれていると感じ、うれしい。 伎芸天へのお供え
伎芸天にはカセットテープやギターのピックが奉納されていた。伎芸天に聴かせるロック!いいじゃん。私も聴いてみたい。 ここには伎芸天の他にも色々な仏がいる。ずいぶんスタイル良すぎるんじゃないの?と言いたくなるような8等身で細身の地蔵菩薩立像や、文様がきれいに残る十二神将、目尻と頬が引っ張られたように上がっている薬師如来と衣が平般な日光月光の脇侍、筋肉のない身体の不動明王、足首からして男性だとわかる帝釈天、蓮華のひとつひとつに鏡餅の模様がある愛染明王など。これらをざっと眺め、伎芸天にまだ名残惜しい気持ちを抱いたまま秋篠寺をあとにした。
御朱印。「薬師如来」とあるが、「伎芸天」と書いてほしかったなぁ。
|