薬 師 寺塔が美しく、坊主が話芸で中学生を笑わせる寺
中宮寺から法隆寺を通ってバス停に戻り、薬師寺へ行くバスを待つ 30分ほど、近くのコンビニでうろうろしたりして時間をつぶす。バスの中で、奈良って田舎だなぁ〜としみじみ思う。聖林寺付近にしろ法隆寺付近にしろ、薬師寺までのバスの車窓からの風景にしろ、のどかだ〜。死ぬ間際まで、この風景が変わらないことを確かめるため、時々奈良に来るべきだなと思う。 薬師寺に着いたのは午後四時だった さすがのメジャー寺も、夕方にもなると修学旅行生は一団体しかいない。しかもやつらは坊主の話に夢中になっており我々一般観光客の邪魔にはならない。思えば私も中学生の時ここで坊主の話芸に笑わされたっけなぁ。聞く気はなくとも今1999年の薬師寺坊主のネタが耳に届いてくる。「GTOっちゅードラマが流行りましたがね、ここはGTYですわ。"グレートテンプルヤクシジ"ちゅーてね」。生徒達ウケてるウケてる。 塔と金堂と講堂とみやげ 夕暮れのせまる古都の空に、1300年の歴史を持つ東塔と、となりに建つ新しい西塔が映える。外人観光客は西塔がお気に入りの様子。だって色彩が綺麗だもんね。 金堂には薬師三尊像。この仏を見て考えたことは、微妙な抑揚表現の豊かさや生の質感がどの程度感じられるかが好きさの度合いの判別ポイントなんだけどそれには「材質」も絡んでくるのかなぁ、ということ。この薬師三尊像は、銅で出来ている。カタい材質なのだ。それなのに頬や腹は柔らかそうに見える。何が材質のカタさを補って柔らかさを作り出しているのかな。でも、少しもトキメかない。微妙な抑揚がないから、天衣や指がつまらない。ツルンとしてテカテカに黒光りしていて、新品みたい。これが白鳳時代の作だなんてホンマかいな。やたらキレイなの。簡単に言うと、清潔。毎日消毒されていそう。つまり、『冷たい』印象なのだ。それはすなわち、材質による印象か? また、「生々しさ」についても考えた。より「生々しい」「まるで生きているかのように見える」と感じられるためには、肉感/柔らかさより、温感/あたたか味が重要視されるのであろうか、と。思い当たったのが法隆寺の百済観音。薬師三尊が『冷たいが柔らかい』であるのに対して、百済観音は『あたたかいがカタい』である。どちらがより「生々しい」かと言えば、私には百済観音の勝ち!に思えるのだ。ということはつまり、金銅仏は素材からしてすでに負け、ということか。そーなのか? さて、これがMy法則として成り立つのかどうか、今後の見仏が楽しみである。
みやげ物売場で「おしゃかさま」という子供向け仏教教育まんがを購入し、唐招提寺へ走った。4時半をすぎてて入れなかった。案内書には「拝観5時まで」って書いてあったのに。廬舎那仏と千手観音だけでもひとめ見たかったのに!しかたなく田舎道をとぼとぼと歩き、バスで奈良駅まで帰った。 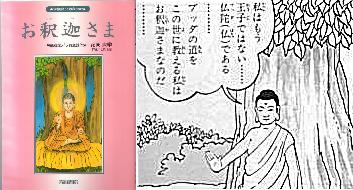 「お釈迦さま」の1コマと表紙 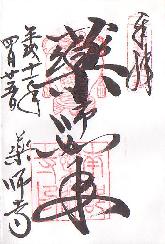 御朱印
|
